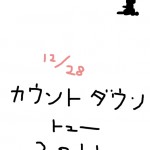カウントダウン・トュー・2011
大掃除にて思う
かつてないほどの大規模な大掃除を、今年のこの時期は敢行している。
ここ数年、いつか使うかもしれない、と思い家のあちこちに溜め込んでいた決して使うことのないモノモノを、勇気を持って捨てることにした。
必要最低限のものだけ残す、という覚悟で家の中を見渡してみると、余りにも必要のないモノが多いことに気づく。いつの間にこんなにモノ持ちになったのか、愕然としてしまう。
これは要らない、あれも捨てる、とみるみるうちにすっきりしていく家の中を見ていると、このまま全てのモノを捨ててしまって、完全な裸一貫になってしまいたいという欲望を覚える。
背中に背負えるだけの荷物を持って、身軽にこの世を生きていけたらどれほど気持ちが良いのだろう。
本当の意味で生きていくために必要なモノの量はどのくらいなんだろう?とゴミを分別しながらぼんやり考えていたりするのだ。
東京大震災で被災した人が、「全てを失ってとてもすがすがしい気分がした」と語っていたのを読んだか聞いたかした記憶がある。不謹慎かもしれないが、僕にはその人の気分がとても良くわかるような気がする。本当は、人間がひとり生きていくために必要なものなんて、カバン一つに収まってしまうくらいのものでしかないのだろう。快適だから、便利だからとモノを増やしていくうちに、気づけばモノに囲まれて身動きの取れなくなった自分がいる。生きていくために、と際限なく買い続けるモノモノは、本当に生きていくために必要なんだろうか?
そんなことを考えながらも、そろそろ新しい冷蔵庫欲しいな、なんて思っている自分もいたりするわけで、これは全く矛盾している。
物欲と捨てたい欲の間でふらふら行ったり来たりしながら、この矛盾もきれいさっぱり捨て去れないだろうか、と願ったりしてみるが、大掃除のようにはいかないようだ。
カウントダウン・トュー・2011
「ひばりは見た!」を私は見た!
幕張メッセで開催された農業ビジネスの展示会を訪れたときのことだ。
会場にはさまざまな種類の、農業に関係した企業がそれぞれの商品を展示している。新型トラクターからビニールハウス用エアコン、はては栽培用蛍光灯、ふだんの僕にはまるっきり縁のない製品がところ狭しとひしめき合っていた。
ふと興味をそそられて、広大な会場を編集者と一緒に歩いてみることにした。
一般人にとってはなかなか目にすることのないものばかりなので、非常に楽しい。
20分ばかり歩き回ったころ、「研究コーナー」とでも呼ぶべき一角に入っていた。
同行していた編集者によると、そこは大学や民間の研究所が開発した、もしくは開発中の製品や技術を展示している場で、企業のスペースと比べるとなんとなく空気が違う。
端的に言うとコマーシャル臭がほとんどしないのだ。
そんな一角の片隅に、なにやら大きな風船のようなものがふわふわと浮いている。
興味をそそられ近づいてよく見てみると、それは透明なビニール素材で作られた飛行船のような形をしていた。大人が両手で抱えられるぐらいの大きさだ。
眺めていると間もなく、担当者らしき男性が話しかけてきた。
一見して営業マンというよりは研究者の風貌。例えれば、大木凡人を少ししゅっとさせたような、独特な雰囲気を持った人だった。
ちょっとだけ笑顔がぎこちないところも、慣れていないことをがんばっているような印象があった。
凡人が説明してくれたところによると、この飛行船はカメラを搭載して上空から写真を撮影するために開発されたということだ。
畑や田んぼの記録用に使ったり、広大な自然公園や湿地を管理している会社などが調査用に利用しているのだという。
手渡してくれたパンフレットを見ると、「簡易空撮気球 ひばりは見た!」と書いてある。
僕はその日本人離れしたネーミングのセンスにまずクラクラしてしまった。
熱心に楽しそうに「ひばりは見た!」の説明をしてくれる凡人を見ていると、とても暖かな気分になると同時に、この彼が「ひばりは見た!」を開発した研究者であることは間違いないという確信を抱いた。
産み出した人間が醸し出すなにかしらの熱が凡人の顔には現れていた。
ひとしきり説明が終わると、隣にいた編集者が口を開いた。彼も興味をそそられたのだろう。
「気球の中にはなにを入れるんですか?」
この風船セットを前にしたら当然の質問かもしれない。彼が言わなかったら僕が質問していただろう。
凡人が胸を張って言う。「ヘリウムです。」
風船にはヘリウムか、それはそうだろう。
編集者が素朴な疑問、という雰囲気でさらに聞く。「ヘリウムってどこで買えるんですか?」
それに対し、凡人はこう答えた。「ガス屋さんです」
ガス屋さん?ガス屋さんって近所にあったっけ?一瞬混乱して戸惑ってしまった僕は、「東京ガスとか、そういう会社ですか?」と間抜けなことを言ってしまった。
凡人はちょっと面白くなさそうな表情を見せ、違います、と即座に否定した。
「そうではなく、ガスを売っているお店です」
すぐに腑に落ちた。あ、なるほど。プロパンガスとか売っているところですね。
凡人もそうそう、と頷いている。
でも僕の家の近所にそういう店はない。
「ひばりは見た!」はたいてい田舎の自然の中で使われるものなのだろうが、例えばそんな都内の人間が「ひばりは見た!」を使おうと思ったら、ヘリウムを求めて遠くまで行かなければならないのだろうか。毎日使うのだとしたら大変すぎる。
そんな疑問を口にした僕に、凡人は「あなた、なにもわかってないですねえ」とはさすがに言わないが、若干冷めた目をして、こう言い切った。
「そういう場合は、風船屋に行けば手に入りますよ」
そうか、風船屋か。
そうそう、え?風船屋?それってどこにあるんですか?
人生思い返してみても僕は風船屋に入ったことがないんですが、風船屋って僕の知らない地方にはけっこうあるものなのですか?
若干パニック気味になった僕に、凡人は真顔でこう言った。
「風船屋ってないんですか?」
研究者という人種のチャーミングな部分を具現化するとこういう言葉になるのだろう。こういう少しズレた感覚が、僕にはとても魅力的に思える。
ちなみに「ひばりは見た!」はタコ糸で釣り竿にくくりつけられている。
「ひばりは見た!」自体には動力がないので、カメラを移動させたい場合は釣り竿を持った人間が移動するということだ。
チャーミングな人間が作ったチャーミングな発明品、それが「ひばりは見た!」の正体だったのだ。
売れるといいな。
シンプル・イズ・ベスト 4
(3のつづき)
“Subway to Jamaica”がデューク・エリントンのヒット曲「A列車で行こう」をベースにして書かれたものだということは、酒で濁った僕の頭でもすぐにわかった。
「急いでハーレムに行きたきゃA列車に乗ろう」というその歌詞から着想を得た話なのだ。
NYの地下鉄は、AもEも途中までは同じ線を走る。
だがAがまっすぐハーレムに向かう急行列車であるのに対して、Eはマンハッタンの真ん中あたりで急カーブを描き、クイーンズの東のほうまで行ってしまう。Eに黙って乗り続けていると終点は「ジャマイカ」という名の駅だ。
甥っ子は飲んだくれて電車の中でうとうとして、気がついたらジャマイカまでたどり着き、やっとのことでハーレムに戻ってきたらもう空は白み始めていて、部屋にはかんかんに怒ったおじさんが待ち構えていた、というただそれだけのお話だ。ちなみに僕自身も酔っぱらって全く同じことをやらかしたことがあるが、それは今は関係ない。
ラングストン・ヒューズが「A列車で行こう」というデューク・エリントンの曲を土台にして短編を書いていた。その事実は、酒のおかげで理性の濃度がいつもより薄くなった僕には、喜び以上に、何かしらの啓示のような重々しさで受け止められた。すなわち、「デューク・エリントンは孤独ではなかった」のだ。
今振り返ってみても、これがまったく筋の通らない話というのはわかっている。
そもそもデューク・エリントンが孤独な人生を送ったという話を過去に聞いたことがあるわけではないのだ。僕はまったく自分勝手に、あれほど美しい曲を作れる人間は孤独な人生を送ったに違いないと決めつけ、デュークの殺伐とした人生のなかに、ラングストンが湧泉のように潤いを与えていたのだ、と信じ込んだ。そんな意味不明の思い込みをされた当のデュークもラングストンも迷惑以外の何ものでもないだろうが、とにかく思い込んだ。
そして、なぜかとても上目線で、デュークのために泣きたくなるくらい幸せな気分になってきた。
じっとしていられない。バーテンダーに紙とマジックをもらい、でかでかと書き込んだ。”DUKE IS NOT LONELY ‘CAUSE LANGUSTON IS THERE.”(ラングストンがいるからデュークは孤独ではなかった)
そのまま紙を四つ折りにして掌の中に入れ、バーを出た。とても重大な新発見をしたかのように気分は高揚していて、これを誰かに伝えたくて仕方がなかった。
少し遠回りして、ヒューズのことを教えてくれたあの女性のアパートに寄り道して、少し迷ってから四つ折りにした紙をドアについたポストに投函した。そのまま我が家まで歩き、高揚感に包まれたまま眠った。
まったく意味を成さない酔っぱらいの所業と言ってしまえば確かにそうだった。
その後一年ほどで僕はハーレムを離れ、さらに三年ほどでアメリカを離れた。過去住んでいた場所なのに、今ではとても遠い場所のように感じることも多い。
もしかしたら一人で高揚感に包まれながら飲んでいたあの夜が、僕がハーレムに最も近づけた瞬間だったのかもしれない。
“DUKE IS NOT LONELY ‘CAUSE LANGUSTON IS THERE.”
そう書かれた紙片はあの女性の日記帳の一ページに貼られたそうだ。
(おわり)
シンプル・イズ・ベスト 3
(2のつづき)
ある夜、友人と飲んだ帰り道。
なぜだか急にもう少しだけ飲みたくなって、ひとりでバーに入った。
一人で特にすることもないので、それほどうまくもない酒を片手に”Best of Simple”を開いて読み始めた。その頃は本の半ばを少し超えたあたりを読んでいた。短い話をいくつか読んだところで、”Subway to Jamaica”という題名の一話に出会った。
その不思議な題名の話には、シンプルさんの甥が登場する。
若くて、やんちゃで、もうはっきりとは覚えていないがアーカンソーだかの田舎から出てきたばかりの甥っ子を、シンプルさんは居候として預かっている。ある夜その甥っ子がいつまでたっても帰って来ないので、やきもきしながらシンプルさんは待っている。やっと甥っ子が帰ってきた頃にはもう外は明け方で、このまま遊び人になってしまうのではないかと危惧したシンプルさんは彼を厳しく叱りつけることにする。甥っ子は怒ったおじさんに対して弁解する。遊んでいたことは遊んでいたが、こんな朝方まで遊んでいた訳じゃない。夜に遊びを切り上げて帰って来ようと地下鉄に乗った。いつものラインに乗ったはずなのに、何時間も乗り続けて気づいたらジャマイカという駅に着いていた、、、。
シンプルさんはその甥の言い訳を聞き、怒る気をなくした、と「私」に語る。こいつはただ電車を間違えただけなんだ。ジャマイカはEラインの終点じゃないか。そして甥に諭す。だから言っただろう、ハーレムに急いで帰ろうと思ったらA列車にのらなきゃなんないんだ。
それで終わり、ただそれだけの話だった。だが不思議なことに、読み終わった僕はつかみどころのない大きな高揚感を感じていた。今振り返っても、酔っぱらっていたからとしか考えられない意味不明の高揚感。僕は”Subway to Jamaica”を読み、なぜだか「デューク・エリントンは孤独ではなかった」と強く感じて、うれしさでいっぱいだったのだ。
(4につづく)
シンプル・イズ・ベスト 2
(1のつづき)
後日、教えられた本を手に入れ読んでみた。
ラングストン・ヒューズはハーレム・ルネッサンスを代表する作家で、もちろん黒人だ。日本では「ジャズの本」の作者として知っている人も多いのかもしれない。その時代以前にはあまり見られなかった、アメリカの黒人自身の視点から、暖かく土臭い情熱を持って書き続けた作家だ。
語弊を恐れずに言えば、現在の日本ではもう半ば忘れ去られた作家なのだろう。本屋や図書館でこの名前を見ることもあまりないが、アメリカでは死後40年以上経った今でも、命を絶やす事なく読み継がれている。
などと取ってつけたように解説してみたが、全てこれは後で知った事柄で、僕がヒューズの存在を知ったのはこのときが初めてだ。僕と同世代の黒人女性が教えてくれたこの”Best of Simple”という本には、この作家が長い月日をかけて書き続けた、ハーレムに住む「シンプルさん」という名のおじさんが主人公の短編ばかりが幾編も集められていた。いわゆるシンプルさんシリーズのベスト盤、といった内容の本だった。
シンプルさんというおじさんは果たしてどのような人物かというと、偉くない金もない見た目もパッとしない、特に賢くもない、という実際にハーレムで普通によく見かける、昼間からくだを巻いているようなおっさんだ。だがこの決して人は悪くないおっさんが、暖かいような情けないようなことをボヤキながら自らの過去や黒人であることの苦しみや楽しさを知人である「私」に語る。それがヒューズが遺したシンプルの物語だ。
しばらくはどこへ行くにも持ち歩いて読み続けた。物語は語り手であるシンプルさんと聞き手の「私」の対話で進んでいく。シンプルさんは酒飲みなので、たいていはハーレムの酒場で一杯やりながらという設定だ。シンプルさんの言葉は、小さく笑ってしまうぐらいくだらないものだったり、ちょっと気分が暗くなってしまうぐらいのシビアな話だったり様々だ。言葉の対象も話によって様々と変化していくが、黒人であること、という一点は決して揺るがない。
読み終わるまでの数日間は、地下鉄の中、喫茶店、バー、ベッドの中、ときには街を歩きながら、時間が許すたびにペーパーバックの本を開きシンプルさんの言葉に聞き入った。アメリカの黒人であるということはどういうことなのかと想像を巡らせながら。
(つづく)
シンプル・イズ・ベスト
ニューヨークに7年間ほど暮らしていた。
絶えず転々とするような引っ越しの多い7年で、街のいろいろな地区をぐるりと住んでまわったのだが、そのなかでハーレムを住所にしていた2年間がある。
言うまでもなくハーレムは住人の多くが黒人の、文字通り黒人の街で、白人はもとよりヒスパニックや僕のようなアジア系はこの街では少数派だった。
住み始めてしばらくすると、近所に呑み友達のような友人ができた。彼らは酔うと、いや酔わなくても黒人であることの誇りと、黒人であることの哀しさについて声高に話し、ときに議論が白熱してケンカのように怒鳴り合ったりもするような若者たちだった。
マルコムXやキング牧師についてはそれ以前から知っていたが、ローザ・パークスやマーカス・ガーヴェイや、その他黒人の長い戦いにまつわる様々な名前を彼らの口から初めて聞いた。
ハーレム・ルネッサンスという言葉を知ったのもこの時期で、たまたま入ったバーでデューク・エリントンの音楽がかかっていて、そのとき一緒にいた女性の口から出てきた言葉だったように覚えている。
その言葉を知らなかった僕に、彼女は説明してくれた。ハーレム・ルネッサンスというのは1919年から始まり十数年つづいた、黒人文化が開花した全盛期だ。文学、音楽、絵画などで後に名作と呼ばれるものが次々と誕生して、黒人の意識と環境が激変した時期でもある、と。
デュークもビリーもベッシーも、みんなハーレムの子供たちなのよ。
少しカッコつけて、全黒人を代表するようにその彼女は言った。
理由は今でもわからないが、僕はハーレム・ルネッサンスというその言葉が、とても大きなものにも小さなものにも、泥臭いような汗臭いような、なんとも判別しがたいドロドロしたものを表しているような落ち着かない気分になって、呑みながら長いこと彼女に質問し続けた。
途中で面倒くさくなったようで、じゃあこの本読みなさい、と言いながら彼女は、バーのナプキンにボールペンで「ベスト オブ シンプル ラングストン・ヒューズ」(Best of simple, Langston Hughes)と書いて渡して来た。
(2につづく)
谷村美月 x AGRIZM
ひさしぶりに女優の谷村美月を撮影した。
彼女を初めて撮影したのは確か06年の初春で、行定勲監督の「ユビサキから世界を」という映画の撮影にスタッフとして参加したときだった。
ロケ地は山形だった。
出発前の東京は汗ばむほどに暖かくなっていたので、まったく何も考えずそのままの身なりでロケに参加したのが大失敗で、初日で粉雪がちらつくほどの凍てつきようの中、骨の芯まで冷え込みながら撮影したのを覚えている。
大体、映画の撮影というのはどういうわけだか徹夜の連続というのが相場になっている。
それが映画の現場は初体験だった僕は、徹夜に対する心の準備と寒さに対する衣服の準備を二重に失敗してしまって、4、5日が過ぎる頃にはもう音をあげる寸前まで追い込まれていた。
休む間もない過酷な現場で、それでもヘコタレていられない、と思わせてくれたのが主演の谷村美月が演技する姿だった。
ストーリー上の設定のため、水をかけられても、泥だらけにされても、あげくの果てには真夜中から夜明けまで顔だけ出して地中に埋められても、文句一つ言わない事はもちろん、キラキラとした演技を淡々と続けていた姿を見てしまっては、水も泥もかけられてなく埋められてもいない僕が音を上げるわけにはいかなくなってしまったのだ。
今回はAGRIZM(アグリズム)という農業系雑誌のグラビア撮影をした。
奥多摩の農家の古民家や田畑をお借りしてのロケになった。農業系の雑誌なのでグラビアも「農」から離れることはないのだ。
レンズを通して数年ぶりに谷村美月を見て、どことなく大人びてきたと思う。それはそうだ。「ユビサキから世界を」のときが彼女は16才で、いまはもう20才になった。その年頃の4年間というのは少女が大人の女性になるには十分な時間だろう。
そうして撮った写真に編集者がつけたタイトルは「登熟期」だった。